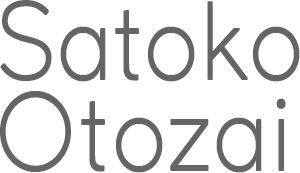
堀江敏幸『その姿の消し方』
ある日、物語の主人公である「私」はフランスの古物市で一枚の古い絵葉書を手に入れます。
何の変哲もない建物の写真があしらわれたモノクロの絵葉書。
そこにはぴったり10行に収まる矩形の形で、抽象的な散文詩のようなものが書き綴られています。
分かっているのは、この絵葉書が半世紀以上前、
アンドレ・Lという男が、ナタリー・ドゥパルドンという女に宛てて出したものであるという事だけ。
この不思議な詩に魅了された「私」は、好奇心に駆られ、このアンドレ・Lなる人物について、
またこの建物について、探索を始めるのです。
物語が描くのは、探索の過程を通じて紐解かれていく、アンドレ・Lの「存在」、そして「不在」が「私」にもたらす時間の概念の変化でしょう。
そして、くるくると相貌を変える詩の意味、その言葉の煌めきが、
時間をかけて主人公の心に沁みわたっていく様子が静かに描かれます。
・・・
消えた光景、消えた人物、消えた言葉は最初からなかったに等しくなる。以前はそんなふうに考えていた。しかし欠落した部分は永遠に欠けたままではなく、継続的に感じ取れる他の人々の気配によって補完できるのではないかといまは思い始めている。視覚がとらえた一枚の画像の色の濃淡、光の強弱が、不在をむしろ「そこにあった存在」として際立たせる。・・・
なんとなくのイメージなんですけど、
以前から、「時間」というものは地続きののっぺりとした絨毯ではなく、
一瞬一瞬が、一枚一枚独立した無機質なカードであって、
その密で規則正しい連続が「時間」なのではないかと、私想像しているのです。
そして、それらの重なったものが「過去」であると思っています。
パリの古物市で、図書目録カードのように分類された絵葉書の木箱を主人公が漁っている場面。
絵葉書が一枚一枚めくられ、手前に重なって厚みを増していくその様、
さらにはその矩形が指に触れる硬い感触も、
私がイメージする「時間」そのものだなあと思いながら読んでいました。
時間を未来に向かうものと捉える時、
私たちはただその絵葉書をめくり続けることしかできません(座礁できない小さなイルカのように)。
いつか新しくめくる絵葉書がなくなってその指がはたと止まるとき、自分自身の存在も消えていくのでしょう。
物語の中で、銀色に髪を染めた女性が、
ぶつかった拍子に中身がばらけて落ちたガム(ちなみにこのガムも四角!)を両手でいっぺんにざあっと搔き集めるというちょっと印象的なシーンが出てきます。
これを見た主人公の「私」は、
「ガムの女性は・・・すばやく搔き集めることでしか得られないものを確実に得ていたのだ」
と表現しています。
また、「私はいつもこんなふうに、唾液にもまれて音を立てている、ガムのような未知の言葉に気を取られて、大切な影を見失ってきた気がする」
とも表現しています。
あの時、この時点で、ざあっと一気に搔き集めることができなかった存在の乱反射、それによって見失ってきた過去の影、つまり欠落部分。それらを見つけて手繰り寄せ、ゆっくりと埋めること、
それは前ばかり向いている私たちに必要なことかもしれません。
物語の終盤、「私」はこのように言っています。
また手紙を書こう、ヴェルデ氏に。ひとことでもふたことでも・・・気持ちを伝えよう。
彼の瞳の色が変わり、言葉が滾るお湯に落ちてしまう前に。
ゆっくりと言葉の煌めきを捉えること、そして誰かの密やかな呼気を慈しむこと。
それによって無機質な時間の連続の中にも吹く風を感じることができる。
そのように、この物語は語りかけてくる気がしました。