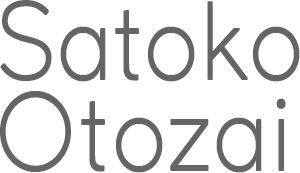
竹内敏晴『声が生まれる』
元々難聴で両耳が聞こえなかった著者でしたが、
16歳の時に右耳の聴力が回復、そこで初めて様々な音に触れるのです。
一般的には幼少期に無意識に獲得する、「ことば」や「声」。
これらを一から手探りで意識的に習得していくこととなった著者。
この本には、著者である竹内敏晴氏の実際の体験談が語られています。
鋭敏な感性で探し続けた、
ことばとは何か、
話すとは一体どういうことなのか。
無自覚に使い捨てている「ことば」というものの奥深さに改めて気づかせてくれる一冊です。
…
わたしの声はじかにあなたを呼び出し、そのからだにふれ、しみてゆき、
動きが起こり、それはそのままわたしに響き、返ってきた声がわたしのからだを内から揺り動かした。
そこに一つの場が生き、「わたし」と「あなた」はじかに響き合っていた…
これが、第一次言語、「まことのことば」の生まれ出る「胎」である。
…
わたしたちは第二次言語によって構成された、制度としての言語によって社会生活を営んでいる。
しかし、第一次言語においていきいきとした充実感をもった表現をつかみ、まことに「生きる」
…
第二次言語とはメルロ・ポンティの主著「知覚の現象学」から竹内氏が引用した表現ですが、
これと似たようなことが、池田晶子氏と大峯顥氏の対談本「君自身に還れ」の中でも語られていました。
たしか、用を足す為だけの言葉と表現されていたかな…
「君自身に還れ」を読んだ時は、社会的言語とは異なる、真の言葉とは何なのかはよく理解できませんでしたが、
竹内氏の本を読んで私なりにちょっと分かった気がしました。
「自然に感応する情動から生まれる声」とでも言えましょうか。
近時、間接的なコミュニケーション方法は様々進化していますね。
直に触れ合うことの大切さを私たちが忘れることはないでしょうが、
人間関係の合理化は今後もより一層進むでしょう。
今や、簡単に距離感なく、誰もがアクセス可能な「わたし」。
それはつまり、世界中どこにでもいる存在であり、
翻っては世界中のどこにもいない存在であるともいえるのです。
身の置き所のない「わたし」と世界の関係は必然、「わたしが世界を知覚する」という方法でしか成立しません。
そして、世界を知覚する為には、その主体となる「からだ」をまず認識することから始めなければなりません。
からだを認識し、世界に触れて、そして「自然に感応する情動から生まれる声」を獲得する。
なんだか、赤ちゃんの成長過程に似てますよね。
この過程では、よりプリミティブな感覚が必要となってくるでしょう。
結局は、どんなに時代が進んでも、どんなに技術が発展しても、
人間として生きる限り、わたしたちは大人の顔をしながら、
生まれたての赤ん坊が辿るような手順に還ることを余儀なくされるように思いますね。
これはどうも、
人間というものの限界のような気もしますし、可能性とも言えるような気もしますし、
私にとっては考える程に面白いことです。